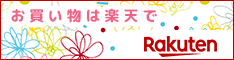地球温暖化を防げる第一歩として、ゴミの減量に協力したいと思いコンポストを購入しました。
前に投稿させていただいた「二酸化炭素削減に向けて」でもコンポストの購入を検討させていただいていました。
今回、ベランダでも置けるタイプのものを購入しました。
コンポストとは
家庭で出た生ゴミを微生物が分解と発酵をすることで堆肥(たいひ)というガーデニングなどの土に変えてくれるものです。
こんポストの種類
段ボール式
価格は安いですが耐久性が弱いところがあります。
密閉型バケツタイプ
密閉しているので、発酵は早いですし、促進剤もいらないです。時々、発酵液を取り出す必要があることと蓋を開けた時の生ゴミ臭があるので、臭いが気になる人には向いていないそうです。
設置型
土の中に埋めるタイプのもので、庭や畑がある方向けです。促進剤入れずにかき混ぜる必要もないようです。
電動生ごみ処理機
機能は、良いですが、価格が高いです。
不織布型
見た目がおしゃれなのと軽く、価格もお手頃だったので、こちらを選びました。
コンポストを使用するメリット
①生ゴミが減ることで、ゴミ処理場での焼却が減り、二酸化炭素が減少します。そのことが地球温暖化を防ぐことにつながります。
②ゴミ袋の使用回数を減らすことができます。ゴミ袋が有料なので使用回数が減ると家計にも優しいです。
③生ゴミの匂いが気にならなくなります。特に夏は臭いが気になるので助かります。
④コンポストで作られた堆肥は、家庭菜園やガーデニングに安全に使用できる土に生まれ変わります。
⑤コンポストの土と触れ合うことで、免疫機能がアップしたり、精神面でもリラックス効果があるそうです。
免疫機能が弱っている方は、微生物によって感染しやすくなるので、お医者様と相談してください。

用意するもの
●発酵材料 生ゴミ、落ち葉など
●土 ガーデニングで使用したり、庭の土など。
●スコップ 土や発酵材料をかき混ぜる時に使用します。
●ハサミ 発酵材料を小さく刻むのに便利です。包丁でもいいと思います。
発効促進と臭い・虫よけ対策できるグッズ
発酵促進(コンポストの微生物の働きを助けることで、生ゴミの分解を早めてくれます)
臭い(ベランダなどの設置では、臭いでご近所様の迷惑にならない対策が必要です)
燻炭(もみ殻をいぶして炭化したもの)・米ぬか・発酵促進剤(ホームセンターやネットで購入できます)
燻炭・米ぬか・発酵促進剤(防臭剤が含まれているものもあります)
虫よけ(虫がわいたりしないようにする必要があります)
燻炭・米ぬか・木酢液・竹酢液
使用方法
①コンポストに土を入れます
容器に半分くらい入れます。
②発酵促進剤を入れます
生ゴミの分解を早めることで臭いの防止になります。購入された袋に入れる量が記載されています。
③燻炭・米ぬか・木酢液・竹炭液などを入れます
悪臭防止や虫除けに入れます。燻炭・米ぬかは、水分調整の役割もあります。
④かき混ぜます
微生物に酸素を取り込むために、一週間に一度かき混ぜます。生ゴミが隠れない時、土を追加します。
⑤熟成
繰り返して、容器がいっぱいになったら、1~2か月かき混ぜずに熟成させます。
⑥完成
熟成させたものは、堆肥になって完成です。
コンポストに入れていいいもの
●果物や野菜のくず
●卵の殻
●茶殻
●落ち葉
●コーヒーかす
●とうもろこしの芯(細かく刻む)
コンポストに入れてはいけないもの
●肉、魚、乳製品
●油分の多い食品
●塩分の多い食品(味噌や漬物など)
●玉ねぎの皮、とうもろこしの皮、栗の皮、タケノコの皮(分解に時間がかかるため)
●ティーパック
●貝殻
●ペットの排泄物
分解するのに時間がかかるものは、悪臭の原因になり、害虫が寄ってきてしまいます。
ポイント
生ゴミを出す時は、小さく刻んで、水分を切ることが大切なようです。
害虫予防にも木酢液や竹炭液をスプレーしておくと良いそうです。
私は、不織布の筒形を2つ購入しました。
2つ購入したのは、生ゴミがいっぱいになったら、1~2か月熟成させなくてはならないので、その間にも生ゴミを入れたかったからです。
助成金について
私の市では、コンポストに対して助成金がでます。
コンポストの助成金は、各家庭2つまでです。
金額は、各自治体で違うと思います。
私は、申請書をダウンロードして、記入した後、市の担当課に提出しました。
購入したレシートか領収書が必要でした。
ネットで購入した場合は、ダウンロードして印刷できます。
これから
まだ、コンポストを始めたばかりでよくわからないことも多いですが、少しでもゴミが削減できるように頑張ってみようと思います。