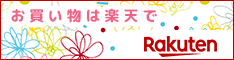スイカが今年は、豊作だそうです。
私の地域では、値段が去年より安くなっています。大きいスイカではなく、小玉スイカを買って食べています。

小玉スイカでも、とても甘くて美味しいです。
スイカについて紹介してみたいと思います。
スイカの起源
アフリカのカラハリ砂漠周辺が起原とされています。その当時のスイカは、種が黒いのは同じですが、果実の色は白で固く、味は苦かったそうです。
品種改良が重ねられて、シルクロードを通り、中国から日本に伝わったとされています。スイカを「西瓜」と書くのは、西の中国からの果物という説があります。
時期については、「鳥獣戯画」の絵巻物のウサギがスイカらしきものを持っているので、平安時代に日本に来たのではないかと言われています。
または、室町時代にポルトガル人から、長崎にスイカが入ってきたのではないかという説もあり、いつかははっきりしていないようです。
スイカの種類
品種改良もされて、国内でのスイカの種類は、20種類くらいあるそうです。
大玉や小玉の他に、黒いスイカや黄色のスイカがあります。中身が黄色は、知っていましたが表面が黄色のスイカはまだ見たことがありません。
種無しスイカもありますし、「ピノガール」という品種は、種ごと食べられます。
日本で一番甘いとされているスイカは、「金色羅皇」という品種です。中身が黄色のスイカで糖度15度を超えるそうです。
糖度15度を例えるなら、メロンや桃、柿と同じ甘さと言われています。
スイカの効能
ビタミンC、カリウム、ビタミンA、βカロテン、シトルリンなどの栄養素が含まれています。
ビタミンC 抗酸化作用があり、シミ予防や美肌効果、免疫力向上に役立ちます。
カリウム 体内の余分なナトリウム(塩分)を排出して、むくみや高血圧の改善に効果があります。
ビタミンA 目や皮膚の粘膜を健康に保ち、免疫機能を維持する効果があります
βカロテン 抗酸化作用があり、皮膚や細胞の健康を保つので美肌効果があります。
シトルリン 血流を改善し、動脈硬化の予防やむくみ解消に効果が期待できます。また、疲労物質を排出してくれる効果もあります。
これらの栄養素は、疲労回復、利尿作用によるむくみ改善効果、水分補給による熱中症対策、抗酸化作用による老化防止や美肌効果、血流改善による動脈硬化の予防、免疫力向上、生活習慣病の予防など様々な効果があります。
スイカの部位ごとの栄養
果肉の部位 水分が多く、ビタミンC、カリウム、β-カロテン、リコピンなどが含まれています。リコピンには、抗酸化作用があるためコレステロールの酸化を防ぐことができ、動脈硬化の予防が期待できます。
白い皮の部位 シトルリンが豊富で、血管を拡張し、血流を改善する効果があります。血流が改善されることで、動脈硬化の予防や疲労回復が期待できます。スイカの緑の皮の部分を削り、薄くスライスしてサラダにして食べたり、冬瓜のようにお味噌汁の具にして食べる方法などのレシピがありました。私は、この部分は捨てていましたが、こんなに効果あるなら捨てるのがもったいないと思ったので、健康のために食べてみようと思いました。
スイカの種 種には、不飽和脂肪酸が多く含まれているため、悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールを増やす働きがあります。スイカの種まで食べることができる品種もあります。スイカの種を食べることには問題はないようですが、種を丸のみしてしまうとそのまま排泄物として排出されてしまうので、よく噛んで食べるといいようです。白い種なら噛んでも固くなさそうですね。
スイカと食べ合わせの悪いもの
油っこいものが良くないようです。唐揚げやてんぷら、ウナギと一緒に食べるとスイカの水分で胃液を薄めてしまい、食物の消化が遅れることで、胃もたれや消化不良を引き起こすとされています。
また、飲み物で利尿作用があるビールやコーヒーなどと一緒にスイカを食べるとスイカにも利尿作用があるため、脱水症状を引き起こす可能性があるとされています。
たくさん食べなければ問題ないので、そういえば程度で思っているといいと思います。
スイカの感想
暑くて食欲がなくてもスイカを食べることで、疲労回復や熱中症予防にもなるのが嬉しいと思いました。真夏の暑い中で育つスイカは、私たちの身体を元気にしてくれる要素がたくさんあり、まさに夏の贈り物だと改めて思いました。